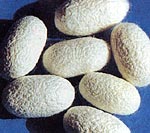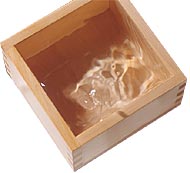|
名草神社【なぐさじんじゃ】
|
|
|
名草神社 ・養父市八鹿町石原
●関連情報 |
●標高760mと日本一高いところにある三重塔 標高1,139mの高さを誇る妙見山の8合目に但馬妙見名草神社はあります。妙見さんは澄みきった聖なる空間に鎮座し、稲の豊作を但馬の内外から多くの農民が列をなして参拝した但馬を代表する神社です。 境内の標高760mのところには三重塔があります。三重塔は出雲大社の境内に出雲国の守護大名である尼子経久が願主となって大永七年(1527年)に建立したものです。妙見社が出雲大社本殿の用材として妙見杉を提供した縁によって、出雲大社から三重塔を譲り受けました。寛文五年(1665年)1月に解体が始められて、船で日本海を渡り、名草神社の境内には5月に上がりました。雪に備えた突貫工事によって9月に竣工しました。 明治37年に国宝に指定されましたが、昭和25年の現在の文化財保護法によって国指定重要文化財となりました。また、昭和62年には解体修理工事が完成し、丹塗りの鮮やかな姿を見せています。 屋根は薄い杉板を何枚も重ね合わせたこけら葺きの屋根です。高さは23.9mもあり、三層目の軒下には四隅に四匹の猿の彫刻が置かれています。「見ざる、聞かざる、言わざる」という三猿は有名ですが、あと一匹は「思わざる」だと言われています。 宝暦四年(1754年)建築の本殿は県指定文化財で標高800mの場所に鎮座しています。正面は9間で、側面が5間あります。屋根は入母屋造という形で、こけら葺きです。正面には千鳥破風があり、その前には唐破風をつけた豪華な造りで、こうした正面から見た姿は日光東照宮の姿に例えられています。 拝殿も県指定文化財で、元禄二年(1690年)の建築です。本殿の前に庭を隔てて相対しており、正面は石垣からせり出すように建てられています。正面が5間で側面が2間あり、中央1間を通路とした形で、割拝殿と言います。名草神社で最も古い建物です。 |