|
城崎温泉【きのさきおんせん】
|
||
| Panorama VRは左右に360度見渡すことができます | ||
|
※QuickTime VRの表示には多少時間がかかりますが、ご了承ください。 |
||
|
2011/06/22 温泉
|
城崎温泉【きのさきおんせん】
|
||
| Panorama VRは左右に360度見渡すことができます | ||
|
※QuickTime VRの表示には多少時間がかかりますが、ご了承ください。 |
||
|
2011/06/22 温泉
|
但東シルク温泉館【たんとうしるくおんせんかん】
|
||
| Panorama VRは左右に360度見渡すことができます | ||
|
※QuickTime VRの表示には多少時間がかかりますが、ご了承ください。 |
||
|
|
鞄【かばん】
|
|

●関連情報 |
●豊岡市を代表する地場産業 我が国で、かばん製造業が産業として興ったのは、明治維新前後と考えらえています。外国人の来訪とともに「トランク」として輸入されたものが「鞄」となりました。一説には、明治6年大阪の商人、山城屋和助がフランスから鞄を持ち帰り、森田直七が模倣して作ったのが日本で初めてとされています。 豊岡では、明治時代の後半、柳行李から生まれた行李鞄から発展していきました。杞柳細工の起源は西暦前27年、 天日槍命(あめのひぼこのみこと)の伝授によるものといわれ、円山川の荒れ地に自生する「コリヤナギ」で籠を編むことから始まり、江戸時代、京極伊勢守高盛が柳の栽培と加工技術を保護し、販売にも力を注いできました。 柳行李は、軽くて堅牢な生活用品の「容器」として、一般大衆に愛され親しまれてきましたが、同じ用途の革製の大型トランクが出現しても「杞柳製トランク」とは呼ばれませんでした。鞄として呼ばれるようになったのは、バンド締め行李に工夫と改良が加えてからで、豊岡市小田井の奥田平治氏が、大正6、7年頃にバンド締め行李に漆を塗り、錠前を取り付け「新型鞄」として、行李にかわって豊岡の鞄として売り出したことが最初とされています。 昭和3年頃には「ファイバー鞄」が誕生し、軽くて強靱で安価、需要も高まり、豊岡の主要産業として発展していきました。さらに、昭和28年頃からビニールテックスなど新素材を取り入れたオープンケースの生産が始まり、輸出もアメリカを中心に急激なのびを見せました。 昭和43年11月には、企業の共同化を進め近代化を図るために、九日市上町に、全国で唯一の「豊岡鞄団地」を設置、機能的な職場環境の確保や積込・運搬の効率化など一層の合理化・近代化をはかった施設として注目を集めました。昭和53年3月には、豊岡鞄会館が、中核施設として新たに大磯町に完成。 品質技術面では、品質ラベルの表示や化学品検査協会登録認定工場制度などにより品質は向上し、生産面でもコンピューターミシンなど新鋭の機械設備が導入されるようになりました。 平成3年3月には、兵庫県商工部が「豊岡鞄産地振興ビジョン」を策定し、デザイン・ファッションの自己表現化、新技術、設備への対応、販売戦略の具体的方策が示され、ファッション化と高級化にポイントを置いた商品開発を目指しています。 平成6年には、国際バッグデザインコンテストを盛大に開催し、世界中からたくさんの作品が集まりました。また、今後の鞄産業の担い手として期待される市内の中学校・高校・短大の学生を対象とした「バッグデザインコンテスト」や、市民公開講座「バッグデザインの基礎知識」を継続して実施し、デザインの高度化、新鮮な発想のオリジナル商品開発、将来の人材確保などに力を入れています。 平成17年には豊岡市内にある宵田商店街通りを「カバンストリート」と呼び、商店街店舗(衣料品店やメガネ店、クリーニング店など)で豊岡の鞄を販売しています。 また、平成18年4月には、特許庁が新たに設けた「地域団体商標制度(地域ブランド)」に出願し、県下で第1号、工業製品としては唯一「豊岡鞄」が登録認定。豊岡鞄を「豊岡ブランド」として全国に広めようという取り組みが行われています。 そして、平成21年4月(2009年)には「カバンストリート」の宵田商店街が、経済産業省の「新・ がんばる商店街77選」に選ばれました。 鞄本来の機能から進んで、あらゆる用途に対応した鞄をつくり出してきた豊岡の鞄産業は、新たな商品開発を進めながら、国内市場はもとより世界を相手に販売網を広げています。 |
2011/06/22 先人たち
|
近藤朔風【こんどうさくふう】
|
||
|
●「菩提樹」「野ばら」「ローレライ」などを訳詞 近藤朔風は、気象測候所の創始者として有名な桜井勉(豊岡市出石町出身)の五男として生まれました。12才の時に近藤家に養子に入り、東京外国語学校、東京美術学校、東京音楽学校で学び、芸術・音楽の見識を高めます。卒業後、『名曲新集』『西欧名曲集』などを発刊し、訳詞家としてその才能を発揮しました。「菩提樹」「野ばら」「ローレライ」「シューベルトの子守歌」などの訳詞は、名訳として絶賛されています。また、日本初のオペラの公演に携わり、日本の近代音楽の発展に貢献しました。 『野ばら』 二、手折りて行かん 野中のばら 三、童は折りぬ 野中のばら (ゲーテ作詞・ウェルナー作曲・近藤朔風訳詞)
|
|
|
松岡の御柱祭(婆々焼祭)
【まつおかのおとうまつり(ばばやきまつり)】 |
|||
|
●松岡の御柱祭(婆々焼祭) 十二所神社前の円山川河川敷で夕刻、老婆に見立てた藁(わら)人形を焼きます。 祭りの由来は、1300年頃、但馬(豊岡市高屋)に雅成親王(後鳥羽上皇第四皇子)が流刑となり、その後を追って、雅成親王の妻、幸姫が京の都からやってきました。その時、幸姫は懐妊の身で急に産気づき、この地で王子を生み落としました。しかし、産後のひだちが悪く、一刻も早く親王のところまで行きたいと、ある老婆に「高屋まであと何日かかりますか」とたずねたところ、老婆は意地悪く「高屋まで九日通る九日市、十日通る豊岡、その先は人を取る一日市で、合わせて20日はかかる」と答えました。 これを聞いた幸姫は、「3日歩けば気力が尽きてしまうほどなのに、これ以上到底生きる望みがありません」と、王子を残し円山川に身を投げてしまいました。 その後、毎年洪水が起き、村人を苦しめたため、その霊を祀ったのが始まりと伝えられています。竹と藁で鉢型の土台を作り、その上部に「御柱松(おたいまつ)」を立て、老婆に見立てた藁人形をくくりつけ、焼き捨てるという奇祭です。 |
||
|
火祭り【ひまつり】
|
|||
|
●湯村の火祭り 新温泉町(旧温泉町)/湯/8月24日 「ジ~ロンボ(次郎坊)、タ~ロンボ(太郎坊)、む~ぎのな~かのク~ロンボ(黒んぼ)」という囃し言葉とともに、子どもたちが弧を描くように打ち振りまわす無数のたいまつの火。「ジ~ロンボ、タ~ロンボ」というのは天狗の名前で、天狗のような驕慢(きょうまん)な心。「む~ぎのな~かのク~ロンボ」は、麦が病気になった黒穂で、害を及ぼすもの。いずれも松明(たいまつ)で焼き払い、五穀豊穣、家内安全、健康を祈願します。春来川の川面に映える火は、暮れゆく夏の夜、幻想的な雰囲気をかもし出します。 |
||
|
●愛宕火祭 ・豊岡市出石町/鍛冶屋伊福部神社/8月24日に近い日曜日 夜、陽が沈む頃、七年山中腹の愛宕(あたご)神社で、木と木をすり合わせて行う「火起こしの儀式」がおこなわれ、愛宕神社の燈明は、地域の若者達によって参道を運ばれます。この火をとって、子どもや、大人の共振りが始まります。パチパチと音をたてて燃え上がる麦ワラの束を縄で持って勢いよく振り廻します。同時に各地区の太鼓保存会によって、火祭太鼓が打ち鳴らされクライマックスを迎えます。 |
|
●万燈の火祭り ・香美町香住区/三谷矢田川河川敷/7月24日 約200年前の江戸中期、まん延した疫病を鎮めるためにはじまったと伝えられています。その後、無病息災や豊作を願う行事として定着しましたが、松明用の麦わらが手に入らなくなり、一時途絶えましたが、昭和59年に復活されました。 |
|
大わらじ・大ぞうり【おおわらじ・おおぞうり】
|
|||
|
●田ノ口賽の神祭 賽(さい)の神は、道を遮り悪霊の侵入を防ぐ「道切り」の神として、古くから人々のあつい信仰を集めてきました。一般的には注連縄(しめなわ)をまつりますが、田ノ口では大きさ約1.5mの大草鞋(おおわらじ)と大草履(おおぞうり)をつくります。朝、氏子たちがお堂に集まってつくり、村の賽の神へ運びます。はしごを使って神木に奉納し、神事がとりおこなわれます。 |
||
|
●安井の大草履 養父市/安井/1月3日 安井地区で、村を守るための厄除け祈願として古くから行われている神事。男たちが、きれいな打ちわらを少しずつ持ち寄って大草履をつくります。作るのは片方だけで、幅約1m、長さ約1.3mという大きなもの。大草履づくりに関わるのは6~7人で、あとの人たちは家族の無病息災を祈願するための小草履を片方ずつ作ります。 |
2011/06/22 観光名所
|
但馬六十六地蔵尊めぐり【たじまろくじゅうろくじぞうそんめぐり】
|
||
|
●六十六地蔵を巡る、但馬の遍路道 但馬全土を巡る総道程約175kmの遍路道。地蔵尊は天日槍伝説に由来します。昔、泥海だった但馬の土地を、新羅の王子・天日槍命が瀬戸の岩山を開き、但馬の平野を開拓した際に、泥がなかなか乾かないため、その地面が固まるように祈願して、六十六の地蔵を祀ったといわれています。日本全国六十六ケ国の但馬版として整備された巡礼道で、心を込めて巡れば、全国をまわるだけの功徳が得られるとされています。最近では森林浴のコースとしても注目を浴びています。 ■六十六霊場札所 7香美町香住区大野 8香美町香住区下岡 |
|
|
海水浴場【かいすいよくじょう】
|
||
 竹野浜海水浴場  気比の浜海水浴場  佐津海水浴場  浜坂県民サンビーチ |
●美しい景観、水質のよい海は海水浴に最適 日本海に面する但馬の海岸は、山陰海岸国立公園に指定されており、変化に富んだ美しい景観の海岸線をもっています。海岸線の入り江に点在する海水浴場はほとんどが遠浅で潮流が少なく、泳ぐのに適しており、毎夏、たくさんの人でにぎわいをみせています。 但馬の海岸はどこも水質のよいきれいな海として知られていますが、中でも竹野浜海水浴場は、約1キロにわたる白い砂浜と遠浅の海、松並木の美しい景観で、明治時代から海水浴場として親しまれてきました。海水浴場としての環境のよさから「日本の水浴場88選」(2001年環境省選定)や「日本の渚100選」にも選ばれています。水の透明度が高いので、スノーケリング、スキューバダイビングなどにも適しています。 また各地の海水浴場は、ほとんどがキャンプ場を併設しており、夏のアウトドアレジャーをぞんぶんに楽しむことができます。【但馬の海水浴場】 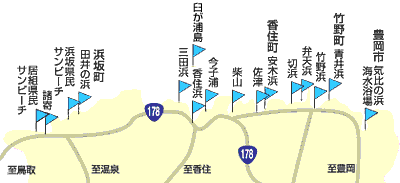
■気比の浜海水浴場(豊岡市) |
|
|
達徳会館【たっとくかいかん】
|
|

達徳会館 |
●豊岡高校の本館として建てられた擬洋風建築物 豊岡市の県立豊岡高等学校敷地内にある達徳会館は、2008年に兵庫県指定文化財に登録された近代化遺産です。1896年、兵庫県豊岡尋常中学校(現豊岡高校)の本館として建築され、市内に現存する明治期の数少ない擬洋風官公庁建築のひとつです。姫路尋常中学(現県立姫路西高等学校)に次いで、兵庫県下で2番目に古い中学校として、神戸尋常中学校(現神戸高等学校)と同年に建てられました。 1941年、校舎の前面改築の時に、この建物の消滅を惜しんだ同窓会組織の達徳会が譲り受け、元から少し離れた現在地に移築されました。以来、この建物は達徳会館と呼ばれ、現在に至ります。 ※同会館は非公開 |