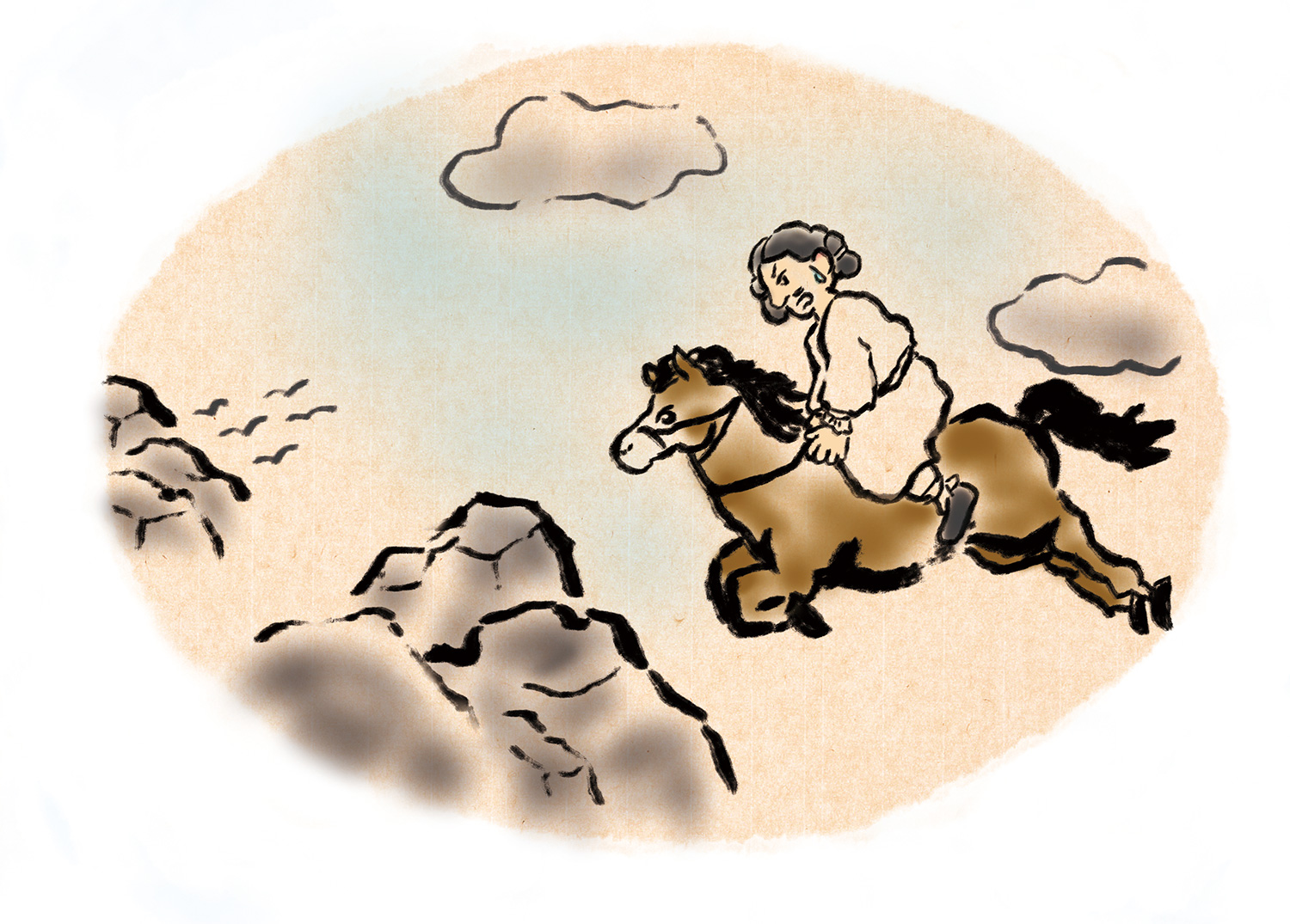|
大引の鼻展望台【おおびきのはなてんぼうだい】
|
||||
|
●240度ぐるりと日本海を見渡せる絶景スポット 香美町香住区の今子浦海水浴場から徒歩5分の断崖の上にある大引の鼻展望台は、日本海を一望できる絶景スポットとして人気です。断崖絶壁の海に突き出た岬の先に展望台があり、遥かに見渡す水平線は息をのむ美しさです。黒島や白石島の他、東側には断層による峡谷や大引洞門、遠方には豊岡市の猫崎半島や京丹後市の経ヶ岬、西側には三田浜海水浴場や国の天然記念物「鎧の袖」や御崎集落のある伊笹岬など、日本海一帯が眺望できます。「日本の夕陽百選」にも認定されており、夏の赤く染まる夕日の景色もおすすめです。初夏から秋口にかけては、日が暮れた後、水平線にイカ釣り漁船の漁火の灯りが灯り、幻想的な世界も楽しむことができます。 |
|||