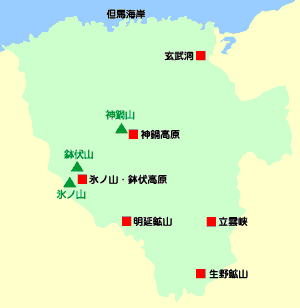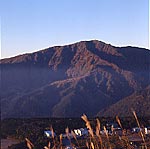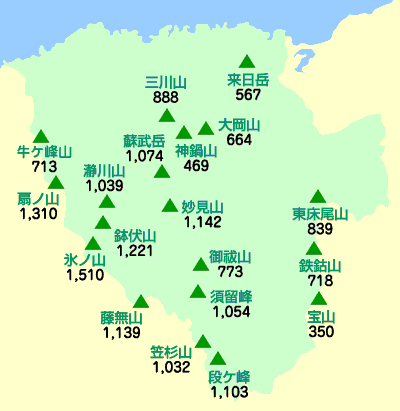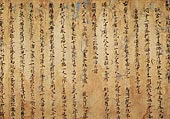|
但馬の地質【たじまのちしつ】
|
||||
|
●但馬の地史 今から約3億年前、アジア大陸の東端は海で、但馬の姿はありませんでした。それから1億年ほど後の造山運動(本州造山運動)で、但馬の陸化が進みました。養父市大屋町一帯に広がる「舞鶴帯」や、福岡県を西端として但馬までのびる「三郡帯」はこのころのもの、「夜久野層群」は少し後にできたといわれています。それから少し経って最初の火山活動が但馬で起こり、花崗岩体の貫入によって、城崎、湯村などの温泉源がつくられました。 2500万年前、海底火山の溶岩が海水と反応して緑色に変化する、グリーンタフ変動が起こり、生野、明延などの鉱山ができました。このころ但馬には海が深く入り込んでおり、村岡には海底面の流跡が残っています。 1000万年前、2回目の大きな火山活動によって、日和山安山岩ができ、古村岡水道が陸化し、数百万年前の火山活動で、鎧の袖(香美町香住区)や宇日流紋岩(豊岡市竹野町)などができました。兵庫県の最高峰・氷ノ山は約300年前、玄武洞の玄武岩は約160万年前の噴火によるものです。 中国地方を東西に走る山脈は、東端の氷ノ山周辺で急に南北の連なりになっており、変化に富んだ但馬海岸の地形とあわせて、かつて但馬が地殻変動の拠点のひとつであったことがうかがえます。 県下で一番新しい火山活動は、約1万年前の神鍋噴火です。また、約2万年前に、最後の氷期が終わって間氷期にはいったころ、現在の豊岡の平野部は海でした。このような、さまざまの変化を経て現在の但馬ができたのです。 ●但馬の地質 ■明延鉱山
|
|||